こんにちは、元裁判所書記官の行政書士、わみです!
(行政書士としてのホームページはこちら(外部リンク))
今回は、
- 行政書士試験に興味があるけどどうやって勉強すればいいの?
- 独学でも合格できる?
こんな疑問を抱いている方に、実際に独学で合格できた勉強法を体験談に基づいてお話ししていきたいと思います!
計画的に、継続的に勉強すれば法律初学者でも独学で合格可能な試験だと思うので、
ぜひ参考にしてみてください!
勉強の方法
行政書士試験の勉強としては、次の4つのステップをしっかり踏んでいけばバッチリだと思います。
- 教科書を通読して全体像を把握する
- 問題集を解いて解説を読み込む
- 過去問を時間を意識しながら解く
- 予想問題を時間を意識しながら解く
では、1つずつ見ていきましょう
1.教科書を通読して全体像を把握する
1つ目のステップは「教科書を通読して全体像を把握する」です
あらゆる試験に共通して言えることであり、宅建の勉強方法の際にも似たようなことを書きましたが、
初心者の状態で問題演習をしても、わからない(問題を解けない)という事実がだけがわかるということになりかねません
「なるほどわからん」というヤツですね
なのでまずは、教科書を読んで知識を入れていくところから始めましょう
加えて、ただ漫然と教科書を読んでいくのではなく、体系的に、つまり自分が何のどこを勉強しているのか全体像を意識しながら読んでいくと頭に入りやすいと思います
法律初学者の場合、憲法や民法などの違いがわからず、自分が試験範囲のどこを勉強しているのか迷子になってしまう可能性があります
何のどこを勉強しているのか意識して、整理しながら知識を入れていきましょう
例えとして、どのジャンルの本がどこにあるのか決められている本棚は、本をしまいやすいですし、取り出しやすいですよね
そんなイメージで頭の中に出し入れをしやすいように知識を入れていく感覚です
1周目にさらっと読んで頭に本棚(体系)を作って、2週目にじっくり読んで本(知識)を入れていく、
というのも良いかもしれません
(ちなみに、体験談でいくと、自分自身は1のステップを踏みませんでした
理由としては、過去の資格試験を通して、法律科目についての体系も知識もある程度完成していたからです
ただ、出題科目は法律科目に限られないため、法律初学者ではない人も1のステップを踏んだほうが丁寧かと思います(少なくとも出題科目を確認して全体像を把握することは必要だと思います)
自分も宅建等の試験は上記のように教科書を読んで体系の把握から始めましたし、知識がなければ行政書士試験も同じように始めたと思います)
2.問題集を解いて解説を読み込む
2つ目のステップは「問題集を解いて解説を読み込む」です
どんな試験でも、知識を身につけるだけでなく、本番でアウトプットしなければなりません
そこで、1つ目のステップで入れた知識をアウトプットする訓練をしましょう
この段階では間違える問題も多いと思います
試験以外の場面では間違えても何も問題ないので、めげずに解いていきましょう
そして、このステップで一番大事なのは解説を読み込むことです
間違っていた問題は当然として、合っていた問題も、選択肢全てを理解した上で当たっていたのか、たまたまだったのかを見極めて、
自分の理解していなかった部分の知識を埋めていきましょう
解説を読んだうえで、理解が足りていなかった箇所については教科書にも戻って知識をより確実のものにしていきましょう
3.過去問を時間を意識しながら解く
3つ目のステップは「過去問を時間を意識しながら解く」です
1でインプット、2でアウトプットして固めていった知識を実戦形式でぶつけていきましょう
過去問を何年分か解いていくと、分野ごとの問題数や繰り返し出題されるポイントなどが見えてきます
また、時間を意識して解くことで、ペース配分や、読むスピードなどもつかめてくると思います
ここでも間違えた問題は解説や教科書をしっかり読んで知識を定着させましょう
何度も教科書を見直した箇所に気づくことができれば、苦手の発見につながり、対策を立てることができます
年ごとに問題の難易度の上下もありますが、このステップのうちに合格点を安定してとれるようになっておきたいところです
(なお、体験談で言えばここでも自分はこのステップを踏みませんでしたが、理由として、
- 2のステップで過去問ベースの問題集を使用していて、正答率も合格水準だった
- 2のステップで試験時間内に解き終わるペースで解けており、調整は4のステップで十分だった
ということがありました
ただ、時間を意識しながら過去問を解くことはあらゆる資格試験において一番重要な試験対策なので、よほどのことがない限りこのステップは省略しない方が良いです)
4.予想問題を時間を意識しながら解く
4つ目のステップは「予想問題を時間を意識しながら解く」です
このステップではできるだけ本番に近い環境で問題に取り組むとよいと思います
時間で言えば、日曜日の同じ時間帯で隔週やってみたり、日にちに余裕がなかったら試験直前期に時間だけはきっちり計ってやってみたり、
環境で言えば、普段とは違う場所でやってみたり、騒音も多少ある環境でやってみたりという感じでしょうか
このステップで安定して解けた問題は本番でも安定して解けますし、間違えた問題はそのままでは間違えてしまうでしょう
本番に一問でも多く得点できるよう、今までの繰り返しになりますが間違えた問題は解説や教科書をしっかり読んで正解できるようにしましょう
自分が使った参考書
自分が使った参考書はTACの「みんなが欲しかった!行政書士の教科書」シリーズです
これ以外でも上記のステップで勉強が進められるものであればどれでも大丈夫だと思います
参考書を選ぶうえで注意すべきことはちゃんと自分が受験する年度版のものを買う、というくらいですかね(法改正があったりするため)
初学者にもわかりやすい説明で、かつ、上のステップを踏んでの勉強もしやすそうだなと思って選びました
まとめ
それでは今回のまとめをしたいと思います!
まず勉強方法については以下の4つのステップ踏んでいきましょう
- 教科書を通読して全体像を把握する
- 問題集を解いて解説を読み込む
- 過去問を時間を意識しながら解く
- 予想問題を時間を意識しながら解く
それぞれのステップは次の通りです
1.教科書を通読して全体像を把握する
- 自分が何のどこを勉強しているのか全体像を意識しながら読んで、体系的に知識を入れていきましょう
2.問題集を解いて解説を読む込む
- 1での知識をアウトプットする訓練をしましょう
- 間違えた問題は解説や教科書の該当部分をしっかり読み込みましょう(3・4ステップも同じ)
3.過去問を時間を意識しながら解く
- 1,2で学んだことを実戦形式でぶつけていきましょう
- ペース配分や読むスピードの感覚もつかんでおきましょう
4.予想問題を時間を意識しながら解く
- できるだけ本番に近い環境で、本番のつもりで解きましょう
参考書については、上の4つのステップが踏めそうなものであればなんでも良いと思います
ただし、きちんと自分が受験する年度版のものを買いましょう
以上です!
自分は上の4つのステップを経て独学で行政書士試験に合格できました
行政書士試験合格を目指したいけど勉強方法に悩んでいる…という方の参考になれば嬉しいです
行政書士のわみでした
(行政書士としてのホームページはこちら(外部リンク))
【次の記事】
第3回 【独学苦手な人向け】行政書士試験の勉強方法2【行政書士】
【関連記事(行政書士試験)】
第1回 行政書士とは・受験のメリット【まずはここから】【行政書士】
【関連記事(他の試験)】
第4回 公務員試験の勉強方法【2次試験・採用面接対策】【公務員試験】
第2回 宅建の勉強方法【独学でも合格できる】【宅地建物取引士】
第3回 【独学苦手な人向け】宅建の勉強方法2【宅地建物取引士】
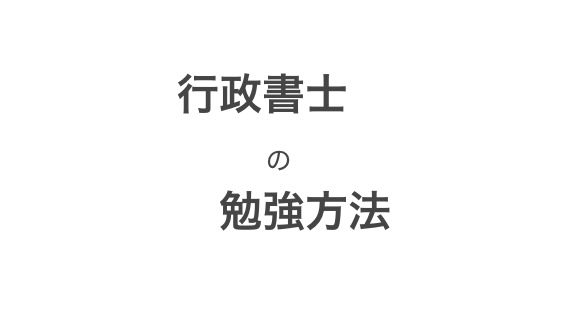

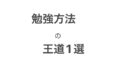
コメント